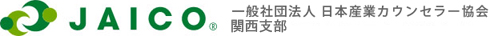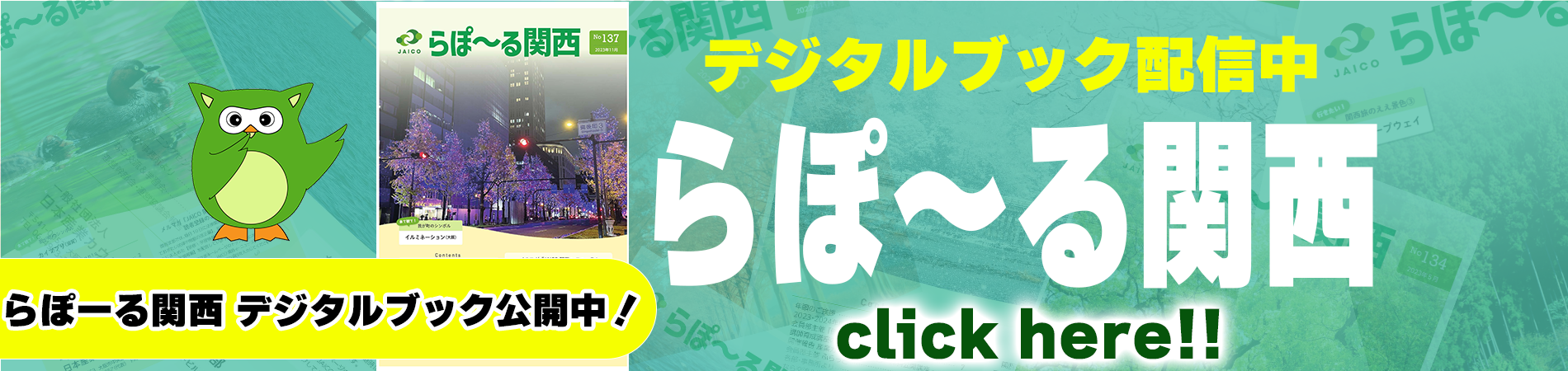新着情報
講座・会員研修情報
【開催中止】2024年4月 会員交流の場「ふらっと」特別版 『第2回オープンダイアローグ学習会』
会員部
テーマ:「開かれた対話による対話(今この瞬間に他者を思いやる)」オープンダイアローグによるリフレクティングを体験してみよう 今回はじめての参加の方も大歓迎です。
開催日:2024年04月18日 (木) 詳しくはこちら
【開催確定】JIC19T12 事例検討と演習で学ぶ「中年期以降の転機への支援」(技能6時間:集合研修)
キャリア
コンサルタント
更新
「中年期の危機」とも呼ばれるライフステージの転機。この転機に直面した相談者のキャリア支援のための講座です。中年期の危機の特徴やキャリア上の課題を学習し、事例検討と演習を通じて相談者の課題解決に繋げるスキルが身につきます。
開催日:2024年04月20日 (土) 詳しくはこちら
【京都事務所】第2回プシュケの会≪追加開催≫「本当の自分に触れる”フェルトセンス”って・・・何?」~ワークで始める「フォーカシング」超入門~
兵庫・京都
事務所
≪ガイド役からひとこと≫ フォーカシングは、自らのこころの声、からだからのメッセージにゆっくりと触れていく方法です。 そうすることで、自分自身をより深く理解し、気づきを得、大切にすることができるようになります。 心理療法の一種と見られることもありますが、セラピーを受けるという事ではなく、自分との付き合い方のテクニック・姿勢と言う方がぴったりきます。 心が毛羽立つような事ばかり見聞きする昨今、ちょっとの間、自分に優しくほっこりしてみませんか? できればこれを機会に、時々でも本当の自分に耳を傾ける習慣を持っていただけると嬉しく思います。
開催日:2024年04月20日 (土) 詳しくはこちら
2024年4月例会「行き違いを防ぐ言い換え術 ~職場ハラスメントの生まれない環境づくり~」
会員部
働く人の悩みの9割は「身近な人間関係」で、特に上司との関係は群を抜いています。 働き方や生き方が多様化し、コミュニケーションツールが多岐にわたり、より一層「ひと言」の意味は重視されています。上司のひと言で「ハラスメント扱いされてしまう」トラブルを防ぎ、信頼関係を構築するために、職場内で言いがちなフレーズの言いかえとポイントについてお伝えします。
開催日:2024年04月21日 (日) 詳しくはこちら
【開催中止】JIC19T05 キャリアコンサルティングの実践的事例検討「キャリアチェンジ」(技能6時間:オンライン研修)
キャリア
コンサルタント
更新
キャリアチェンジ(主に転職・再就職のケース)を対象としたキャリアコンサルティングの場面での事例を検討することにより、キャリアチェンジの抱える課題を理解し、キャリアコンサルティングの専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。
開催日:2024年04月21日 (日) 詳しくはこちら