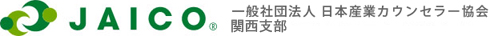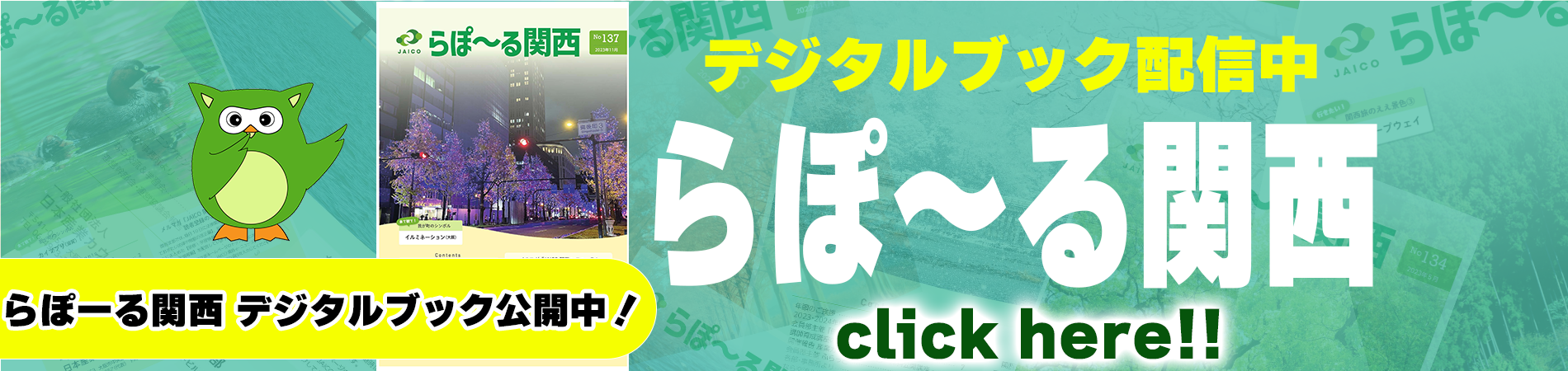新着情報
講座・会員研修情報
【開催中止】【修了証は2024年5月8日以降発行】JIC17T09 「女性の組織内キャリア」(キャリアコンサルティング事例検討・技能講習)(技能6時間:オンライン研修)
キャリア
コンサルタント
更新
女性を対象としたキャリアコンサルティングの中でも、組織内キャリアを形成する上での課題に焦点を当てた講習です。 組織内で女性がキャリアを形成していく上で直面し乗り越えなければならない課題を理解し、キャリア形成上の課題の見立て・キャリアコンサルタントの対応の視点を深め、実践的な対応力を身につけます。 ★当講習は下記講習の内容をリニューアルしたものです。すでに旧講習名で受講し修了されている方は、当講習を受講されても更新条件の時間数は加算されませんので、ご注意下さい。 旧講習名:JIC17T09 キャリアコンサルティング事例検討「女性」実践編(技能講習)
開催日:2024年04月28日 (日) 詳しくはこちら
【満員御礼】【修了証は2024年5月13日以降発行】JIC17T02 「女性」基礎編(キャリアコンサルティング事例検討)(技能6時間:集合研修)
キャリア
コンサルタント
更新
結婚・離婚・出産・育児・介護…女性のキャリア形成にはストレスフルなイベントが数多くあります。 本講習では、女性を取り巻く環境や抱える課題を客観的に理解した上で、 キャリア形成上の課題の見立てと支援が行えるよう、実践的な対応力を身につけます。 ★当講習は下記講習の内容をリニューアルしたものです。すでに旧講習名で受講し修了されている方は、当講習を受講されても更新条件の時間数は加算されませんので、ご注意下さい。 旧講習名:JIC17T02 事例に学ぶ女性へのキャリアコンサルティング基礎編(技能講習)
開催日:2024年05月03日 (金) 詳しくはこちら
【開催確定】【修了証は2024年5月13日以降発行】JIC22T02 キャリアコンサルティング・プロセス毎のかかわり(技能6時間:オンライン研修)
キャリア
コンサルタント
更新
キャリアコンサルタントには相談過程全体をマネジメントできるスキル、つまり、相談者の抱える問題の把握を的確に行い、相談過程のどの段階にいるかを把握し各段階に応じた適切な進行・管理ができること、が求められています。この講習ではキャリアコンサルティングのプロセスについて多種多様な考え方・とらえ方を知り、コンサルタントとして相談者にどのようにかかわっていくか、事例も通してプロセス毎のかかわり方を理解し、プロセス・マネジメント・スキルを身につけていきます。 ★当講習は以前開講していた”キャリアコンサルティング・プロセス理解(旧講習コードJIC17T05)”を全面的に刷新し、新たな講習(講習コードJIC22T02)としたものです。 過去JIC17T05を受講された方も、あらためて当講習を受講修了すれば、更新条件の技能講習修了時間に加算されます。
開催日:2024年05月04日 (土) 詳しくはこちら
【開催確定】【修了証は2024年5月13日以降発行】JIC19T02 事例に学ぶ「発達障害の理解と対応」(技能6時間:オンライン研修)
キャリア
コンサルタント
更新
発達障害の問題と対応についてより深く理解し、キャリアコンサルティングの専門家にふさわしい見識と実践的な力を身につけます。
開催日:2024年05月06日 (月) 詳しくはこちら
【R02】講師に関連する法令(オンライン研修)
研修部
この講座では、労働安全衛生法、労働災害防止計画などメンタルヘルス対策の根拠となる規定など企業で人事や産業保健スタッフ、産業カウンセラーとして働く上で必要な知識を社会保険労務士である講師経験豊富な講師から学びます。 産業カウンセラーとして働く中で、社内研修を企画、実施する機会や、外部講師として依頼を受け、企業や学校に出向き講義を行う機会が増えています。講師として活動するうえでも必要な知識の修得を行います。これから講師として活躍するにあたっての基礎を身につけてみませんか。 ※本講座は講師育成講座(基礎研修)「講師に関連する法令」に該当します。
開催日:2024年05月11日 (土) 詳しくはこちら